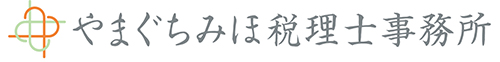贈与に関するご相談を受けることはよくあります。特に、贈与税には2つの課税方式があるため、混乱される方も少なくありません。
贈与税の2つのしくみについてご紹介します。
贈与税のしくみの前にー基本の確認
贈与は「双方の同意」が必要です
贈与は、あげる人と、もらう人の、双方の同意があってはじめて成立します。
「双方の同意」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、「あげます」「もらいます」という認識があることです。
口頭でのやり取りでも贈与は成立しますが、双方の同意があったことを明確にするため、贈与契約書などの書面で残しておくことをおすすめします。
贈与税を支払うのは誰?
贈与税がかかる場合、その税金を支払うのは贈与を受けた人です。
贈与を受けた人が申告し、納税を行うことになります。 一方で、贈与をした人は贈与税の申告や納税は必要ありません。
贈与税の2つの課税方式
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの制度があります。 それぞれの制度は、贈与をしたときや、その後に贈与をした人が亡くなったときの扱いが異なります。
暦年課税
暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)でもらった贈与の合計額に応じて贈与税がかかる制度です。
もらう人ごとに年間110万円までの贈与は非課税で、この枠を超えた分について、10%~55%の超過累進税率で贈与税がかかります。
この制度で贈与をした場合、贈与をした人が亡くなったとき、相続開始前3年以内に行った贈与(令和6年以降の贈与に関しては、7年以内)に行われた贈与は、相続財産に加算されます。
加算されるということは、その贈与分も相続税の対象になるという意味です。
なお、相続で財産を受け取らない人については、この「加算」の対象にはなりません。
相続時精算課税
もうひとつの制度が「相続時精算課税」です。
こちらは、贈与する人ごと・もらう人ごとに、累計2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。
また、令和6年以降の贈与については、上記に加え、毎年110万円までの贈与は非課税となりました。
この制度は、贈与する人、もらう人に条件があります。
相続時精算課税を選ぶと、贈与された財産はすべて、贈与した人が亡くなったときに相続財産に加算されます。(令和6年以降の毎年110万円までの非課税枠は、相続財産に加算されません)
相続税精算課税は、一度この制度を選択すると、暦年課税には戻れません。そのためこの制度の選択は慎重に行う必要があります。
どちらのしくみを選ぶべきか
贈与税のどちらのしくみを使うかは、以下のような事情によって選択が変わってきます。
- 贈与する方の財産額
- 贈与する方の相続までどれくらの期間を見込むか
- 贈与する相手(例:子・孫)
- ご家族の関係性
実際のご相談では、税金のことだけでなく、家族間のバランスをどう取るかが大きなテーマになることも多いです。
たとえば、長男家族と長女家族それぞれに贈与した場合、家族の人数が異なると、受け取る金額に差が出てしまうことがあります。 こうした差が、将来的なトラブルの原因になってしまうこともあるのです。
おわりに
贈与税には2つのしくみがあり、さらに相続との関係もふまえる必要があるため、分かりづらく感じられるかもしれません。
贈与について分からないことがある場合は、税理士にご相談いただくことをおすすめします。
相続、贈与に関するご相談を承っております
おひとりでのご相談はもちろん、ご家族ご一緒でのご相談も可能です。