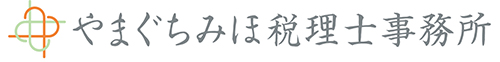相続税対策として、生前贈与を検討されている方も多いでしょう。
令和6年(2024年)からは、相続税に足し戻される期間が「3年以内」から「7年以内」に延びたことは、すでにご存知かもしれません。
ただし、足し戻されるのは「すべての贈与」ではありません。
相続が発生したときに相続財産へ足し戻される贈与と、足し戻されない贈与についてご紹介します。
相続財産に足し戻される贈与
贈与税には
- 暦年贈与(毎年110万円までは贈与税がかからない方式)
- 相続時精算課税(生前にまとめて贈与できるが、相続時に精算する方式)
の2つの仕組みがあります。
「生前贈与加算」というルールでは、亡くなった人(被相続人)から相続人などに行った贈与額を、相続財産に加算して相続税を計算します。
- 令和5年まで:亡くなる前 3年以内 の暦年贈与が加算対象
- 令和6年以降の贈与:亡くなる前 7年以内 の暦年贈与が加算対象
7年すべてが適用されるのは、相続開始が令和13年(2031年)以降の場合です。
また、贈与税がかかったかどうかは関係なく、年110万円以内の贈与でも加算されます。
相続財産に足し戻されない贈与
足し戻しの対象となるのは、亡くなった人の財産を相続によって取得した場合です。
孫への贈与は、相続時に孫が財産を取得しない場合は加算されません。
しかし、次のような場合は加算の対象になりますので注意が必要です。
■孫が死亡保険金の受取人になっている場合
相続時に保険金を受け取ると、「相続財産を取得した」とみなされ、贈与分も加算されます。
加算を避けたい場合は、孫を保険金の受取人にしないことがポイントです。
■遺言書で孫に財産を渡す場合
遺言によって孫が財産を受け取ると、その時点で相続財産を取得したことになり、贈与分も加算されます。
また、相続人であっても、相続時に一切財産を受け取らなければ加算されません。
例えば、生前に十分な贈与を受けていて相続では何も受け取らない場合です。
令和6年以降の相続時精算課税では、年間110万円以内の贈与については、相続時に加算されないことになりました。
相続開始の何年前の贈与であっても、加算されません。
贈与の使い分けが大切
贈与を行う際は、
- 相続人に贈与するのか、相続人以外(孫、子の配偶者など)に贈与するのか
- 相続財産の規模はどのくらいか
を踏まえて、暦年贈与と相続時精算課税を上手に使い分けることが大切です。
贈与税のルールを正しく理解し、ご家庭に合った相続税対策を進めていきましょう。
迷ったときは、専門家である税理士にご相談ください。
相続、贈与に関するご相談を承っております
おひとりでのご相談はもちろん、ご家族ご一緒でのご相談も可能です。